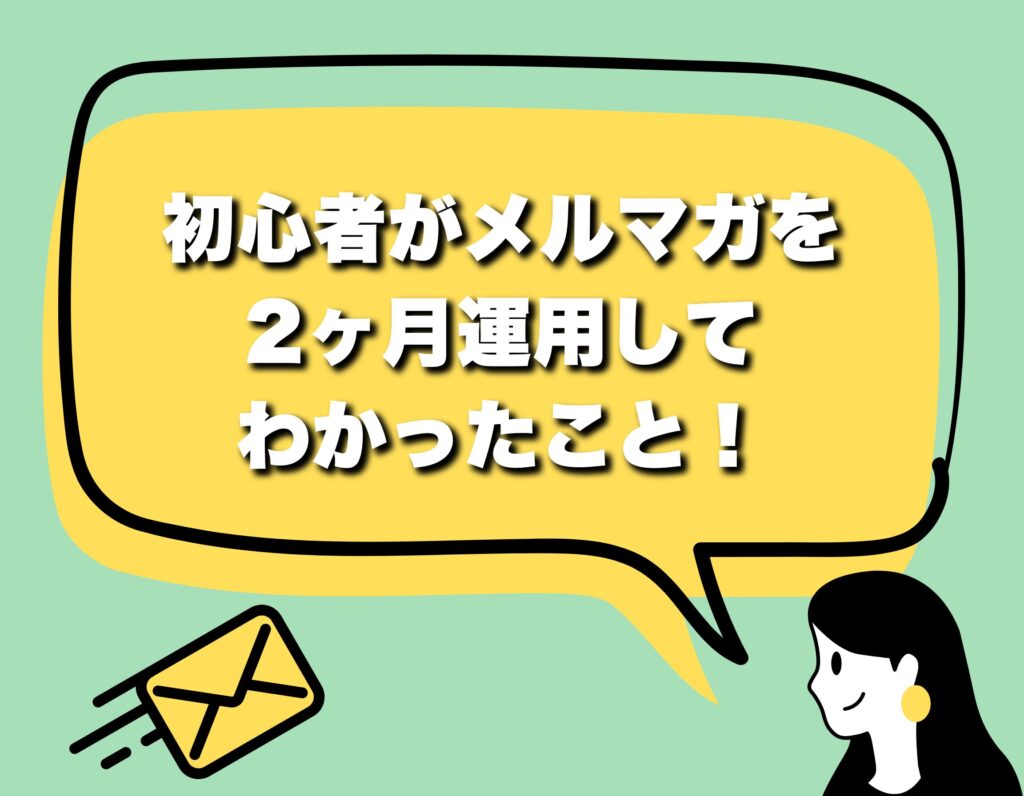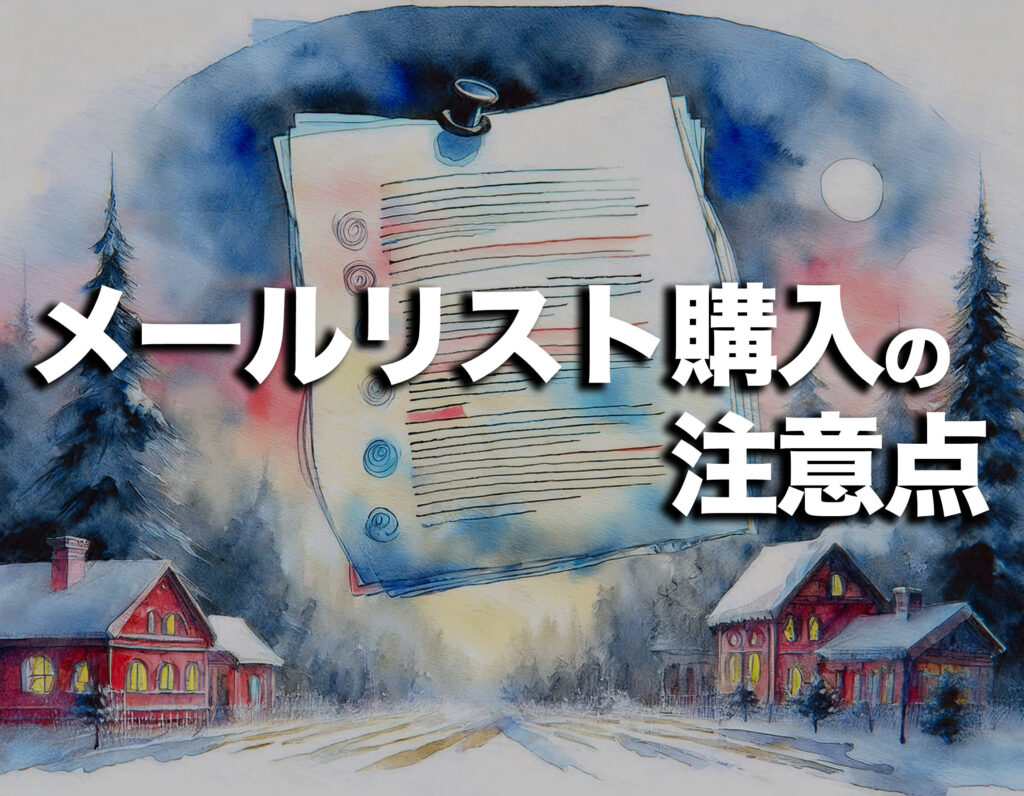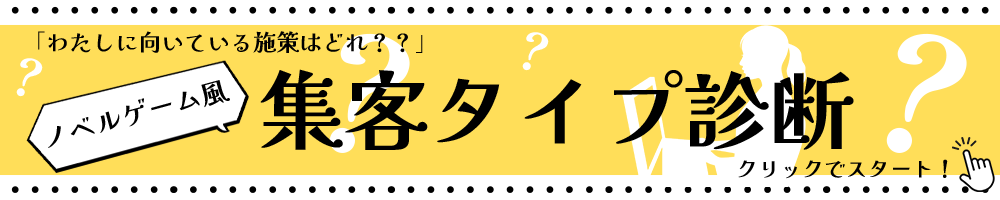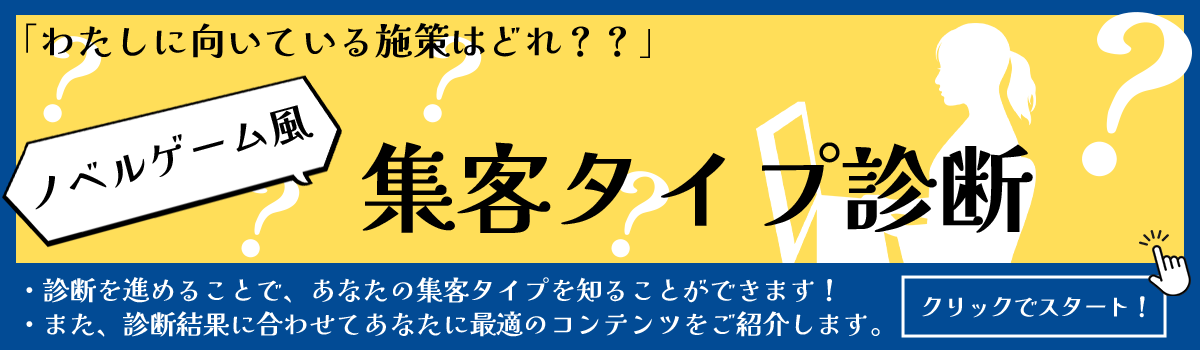メルマガの数値を見ていたら、
配信停止率っていうものがあったぶん…
なんだか、こわいぶん😨😨😨


数値を見て分析するのは、とても大事なことだよね!
それじゃ、今回はメルマガ分析で重要な「配信停止率」について解説していくね✨
メールマガジンの効果を客観的に測る上で、配信停止率は非常に重要な指標です。
「オプトアウト率」とも呼ばれ、配信したメールに対して読者が配信停止を行った割合を示します。
この数値が高い場合、読者のニーズと配信内容にずれがある可能性を示唆しています。
配信停止率を無視することはできません。
なぜなら、単に購読者が減るだけでなく、顧客リストの価値低下や売上の減少、さらにはブランドイメージの悪化といった深刻な問題を引き起こす可能性があるからです。
そこで今回は、配信停止率の基本的な意味と計算方法から、業界のベンチマーク、そして配信停止率が高くなる根本的な原因と具体的な改善策について詳しく解説!
これらの知識と実践的なヒントを活用して、メールマーケティングの効果を最大限に高め、読者との健全な関係を築くための第一歩を踏み出しましょう!
ページコンテンツ
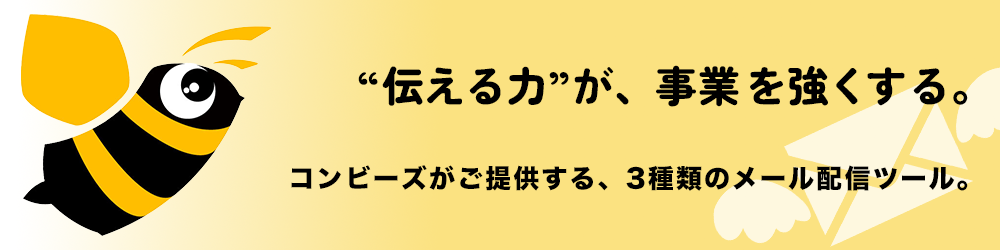
配信停止率の基礎知識
まずは、配信停止率の基礎知識を確認していきましょう!
配信停止率とは?その計算方法
配信停止率とは、配信したメールマガジンに対して、読者が配信停止手続きを行った割合を示す指標です。
「オプトアウト率」とも呼ばれ、メールマーケティングの効果を測る上で重要な数値です。
この率が高い場合は、配信内容と読者のニーズが合っていない可能性を示唆しています。
計算方法は以下の通りです。
| 配信停止率(%)=(配信停止数÷有効配信数)×100 |
ここで言う「有効配信数」とは、送信したメール総数から、宛先不明などでエラーとなった数(バウンス数)を差し引いた、実際に読者の受信ボックスに届いたメールの数を指します。
例えば、
| 配信したメール数:10,000通 エラー数:100通 配信停止手続きを行った人数:45人 |
の場合、以下の計算式で配信停止率が算出できます。
| 45÷(10,000−100)×100≒0.45% |
この数値を定期的に計測し、変化を追うことで、顧客の反応やコンテンツの質を客観的に把握し、改善に向けた具体的なアクションを検討できます。
配信停止率が高いと何が起こる?
配信停止率の上昇は、単にメールを送る相手が減るだけでなく、ビジネス全体に様々な悪影響を及ぼします。
リスト価値の低下
苦労して集めた顧客リストも、配信停止が増えると価値が下がってしまいます。
リストの価値が落ちると、将来の売上を逃すことにつながり、失った分を補うためには、新規顧客獲得のコストがよりかかってしまいます。
売上への直接的な影響
メールマガジンは、新商品やセール情報を届け、顧客の購買意欲を高める重要なチャネルです。
配信停止は、こうした情報が届かなくなることを意味し、リピート購入の機会を失うことにも繋がります。
結果として、顧客一人ひとりの生涯価値(LTV)が低下し、長期的な売上の安定を損ないます。
ブランドイメージへの悪影響
読者が配信停止を選ぶ背景には、「内容が役に立たない」「配信頻度が多すぎる」といった不満が隠れています。
このようなネガティブな体験が積み重なると、企業やブランドそのものへの印象が悪化しかねません。
最悪の場合、迷惑メールとして報告されたり、SNSなどで悪い評判が広まるリスクも高まります。
業界平均とベンチマーク
自社の配信停止率が高いのか低いのかを判断する上で、業界平均との比較は有効な手段です。
一般的な目安として、健全な配信停止率の水準は0.5%未満とされています。
この数値を超えている状態が続くようであれば、何らかの対策を検討すべきサインと言えるでしょう。
ただし、この数値はあくまで参考値です。
最も重要なのは、他社と比較すること以上に、自社の過去のデータと比較し、数値が悪化傾向にあるのか、改善傾向にあるのかという「変化」を捉えることです。
その上で、目標とすべき現実的な数値を設定し、改善活動に取り組むことが成果への近道となります。
配信停止率が上がる原因と改善策
配信停止率が上昇している場合、その背景には複数の要因が絡み合っています。
漠然と「何かが悪い」と捉えるのではなく、原因を具体的に特定し、それぞれに合った対策を講じることで初めて改善へとつながります。
ここでは、主な原因とそれに直結する改善策を解説します。
原因1:コンテンツのミスマッチ
配信しているメールの内容が、読者の期待や関心と合っていない場合、配信停止の大きな原因となります。
改善策:ターゲットに合わせたパーソナライズ
読者の興味関心や行動履歴を分析し、それに合わせたパーソナライズされたコンテンツを意識することが重要です。
セグメンテーション
顧客の属性(年齢、性別、居住地など)や行動履歴(購入履歴、閲覧履歴など)に基づいて、配信リストを細かく分類します。
例えば、特定のカテゴリの商品を購入した顧客には、その関連商品の情報を送るといった方法です。
セグメントの再評価
顧客の興味や行動は時間とともに変化します。
最初に設定したセグメントが現状に合っているかを定期的に見直し、常に最適なメールを配信しましょう。
原因2:配信頻度やタイミングの不適切さ
メールの配信頻度やタイミングも、配信停止率に直結する重要な要素です。
配信頻度が多すぎると読者に煩わしさを感じさせ、少なすぎると忘れられてしまう可能性があります。
改善策:配信頻度と時間帯の最適化
読者の負担を減らし、エンゲージメントを高めるために、配信頻度や時間帯を見直しましょう。
配信頻度の調整
顧客セグメントごとに最適な頻度を見つけることが効果的です。
多くのメール配信ツールには、読者が自分で配信頻度を選択できる機能が備わっているものもあります。
配信時間帯の最適化
読者がメールをチェックしやすい時間帯に配信することで、開封率やクリック率の向上が期待できます。
一般的に、BtoCの場合は通勤時間帯や休憩時間、帰宅後の夜などが開封されやすいとされています。
原因3:メールタイトルや導入文の魅力不足
メールのタイトルや導入文は、読者がメールを開封するかどうかを判断する最初のフィルターです。
ここが魅力的でないと、そもそもメールを開いてもらえず、配信停止につながるケースが少なくありません。
改善策:件名・冒頭文の改善による開封率アップ
メールの件名や冒頭文には、読者が得られる具体的なメリット、数字や記号、緊急性、好奇心を刺激する要素を含めることが効果的です。
| 具体的なメリットを提示する:「【限定】人気商品が20%OFF」のように、読者が得られるメリットを明確に示しましょう。 パーソナライズする:読者の名前や興味のある商品名を入れることで、特別感を演出できます。 A/Bテストの活用:1通のメールからでもすぐに試せるため、A/Bテストなどを活用しながら、効果的な表現を見つけることが大切です。 |
原因4:配信リストの精度問題
メールを届けるリストそのものに問題がある場合も、配信停止率を高める原因となります。
改善策:不要アドレスの整理とリストメンテナンス
配信リストの精度を維持することも、配信停止率を改善する上で重要です。
| リストクリーニング:長期間メールを開封していない読者や、エラーが頻繁に発生するアドレスは、リストから削除するクリーニングを定期的に行いましょう。 リエンゲージメントメール:一定期間(例えば3ヶ月〜6ヶ月)メールを開封していない読者に対しては、まず「メール配信を継続しますか?」といった確認メールを送ることが有効です。 反応がない場合は、リストから除外することを検討します。 |
原因5:法令やガイドライン違反
メールマーケティングを健全に運用するためには、「特定電子メール法」などの法令を遵守する必要があります。
配信停止手続きが分かりにくい場合、読者は配信停止ではなく「迷惑メール報告」を選択する可能性が高まります。
またGmailについてはGoogleの定めた「メール送信者のガイドライン」を守ることも重要です。
改善策:法令遵守と透明性の高い配信ポリシー
配信リストの健全性を維持し、読者からの信頼を失わないためには、法令遵守と透明性の高い配信ポリシーが不可欠です。
特定電子メール法への対応
メールを配信する際には、必ず「特定電子メール法」を遵守する必要があります。
具体的には、メール本文に送信者の氏名や住所、問い合わせ先を明記し、受信者がいつでも簡単に配信を停止できるリンクを明記することが義務付けられています。
ユーザーフレンドリーな設計
配信停止の導線を分かりやすく設計しましょう。
こうした取り組みは、長期的なブランド価値を守る上で最も重要な要素の一つです。
ガイドラインを尊守する
各メーラーのルールを守らなければ、それぞれからスパムと認定されてメールが届かなくなる可能性があります。
たとえばGoogleのGmailについてのガイドラインである「メール送信者のガイドライン」では、メールドメインに以下のようなメール認証を設定しなければなりません。
| ・すべての送信者: SPF または DKIM ・一括送信者: SPF、DKIM、DMARC |
これらはなりすましメールなどの悪質な配信を事前に防ぐことを目的としています。
配信停止率を下げて、成果を見える化する3つの方法
配信停止率の改善は、メールマーケティング担当者にとって重要なミッションです。
しかし、改善活動は実施して終わりではなく、その成果を正しく「見える化」し、社内へ報告することで、はじめて活動の価値が認められます。
改善前後の数値比較とレポート化
改善活動の成果を客観的に示すには、数値を使ったレポート作成が不可欠です。
感覚的な報告ではなく、具体的な数字に基づいて説得力のある報告を目指しましょう。
| 主要なKPIの比較:配信停止率、開封率、クリック率といった指標を、改善策実施前と実施後で比較します。 施策ごとの効果測定:件名改善、配信頻度の見直し、リスト整理など、行った施策ごとにどのような効果があったかを分析します。 顧客セグメントごとの変化:特定の顧客セグメント(新規顧客、優良顧客など)ごとに配信停止率やエンゲージメントの変化を分析することも重要です。 |
これらの数値をグラフや表を使って視覚的に分かりやすくまとめることで、報告の説得力は格段に高まります。
経営層・上司への報告ポイント
経営層や上司は、事業全体の目標達成に直結する情報を求めています。
そのため、単なる数値改善の報告に留まらず、その改善が会社にもたらすメリットを明確に伝えることが重要です。
| 事業目標との紐づけ:配信停止率の改善が、最終的にLTV(顧客生涯価値)の向上や新規顧客獲得コストの削減にどう繋がるかを説明します。 次のアクションプランの提示:改善成果を報告する際は、必ず今後の展望や次のアクションプランもセットで提示しましょう。 具体的なコスト削減効果:不要なアドレスへの配信を停止したことで、「年間〇円のコスト削減が見込める」といった具体的な数字を提示することで、より強く成果をアピールできます。 |
まとめ
メールマーケティングにおける配信停止率は、単なる数値以上の意味を持ちます。
これは、読者がコンテンツにどれだけ価値を感じているか、そしてブランドとの関係性が健全かを測る重要な指標です。
配信停止率が高い状態が続くと、顧客リストの価値低下、売上機会の損失、さらにはブランドイメージの悪化といった、ビジネス全体に悪影響を及ぼす可能性があります。
このため、配信停止率を改善することは、メールマーケティングの効果を高めるだけでなく、顧客との長期的な関係を築き、最終的にビジネスの成長へとつなげるために不可欠です。
配信停止率を改善するためには、原因を特定し、適切な対策を講じることが重要です。
今回の記事で紹介した具体的な改善策は、以下の通りです!
| コンテンツのパーソナライズ:顧客の属性や行動履歴に合わせてメールをセグメントし、読者が本当に興味を持つ情報を提供することで、エンゲージメントを高めます。 配信頻度と時間帯の最適化:読者に負担を感じさせない最適な頻度とタイミングでメールを配信し、開封率とクリック率の向上を目指します。 件名・導入文の改善:読者の注意を引き、メールを開封してもらうための魅力的な件名を作成します。A/Bテストを活用して、効果的な表現を見つけましょう。 配信リストの整理:長期間反応がないアドレスやエラーが多いアドレスを定期的にクリーニングし、リストの質を高く保ちます。 法令遵守と透明性の確保:特定電子メール法を遵守し、配信停止の導線を分かりやすくすることで、読者からの信頼を維持します。 |
これらの施策を実践し、改善前後の数値をレポート化して分析することで、その成果を可視化できます。
そして、その成果が最終的にビジネスにどのようなメリットをもたらすかを明確に伝えれば、社内での評価も高まり、さらなる改善活動への推進力となるでしょう!
この記事が、あなたのメールマーケティングの改善とビジネス成長の一助となれば幸いです。
メール配信ならコンビーズ
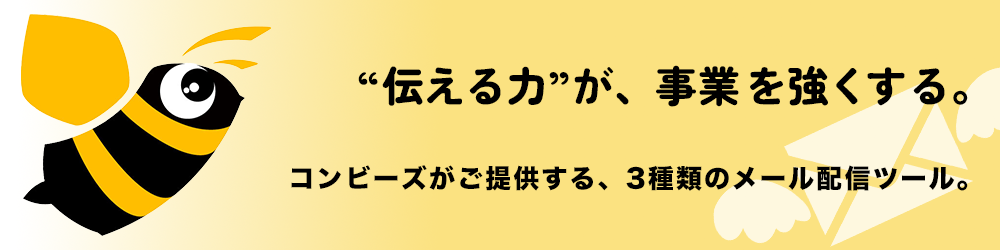
この記事のライター
川上あおい
3児の母。株式会社コンビーズのライター。メルマガも担当。24時間、車を運転したことがある。

この記事の監修
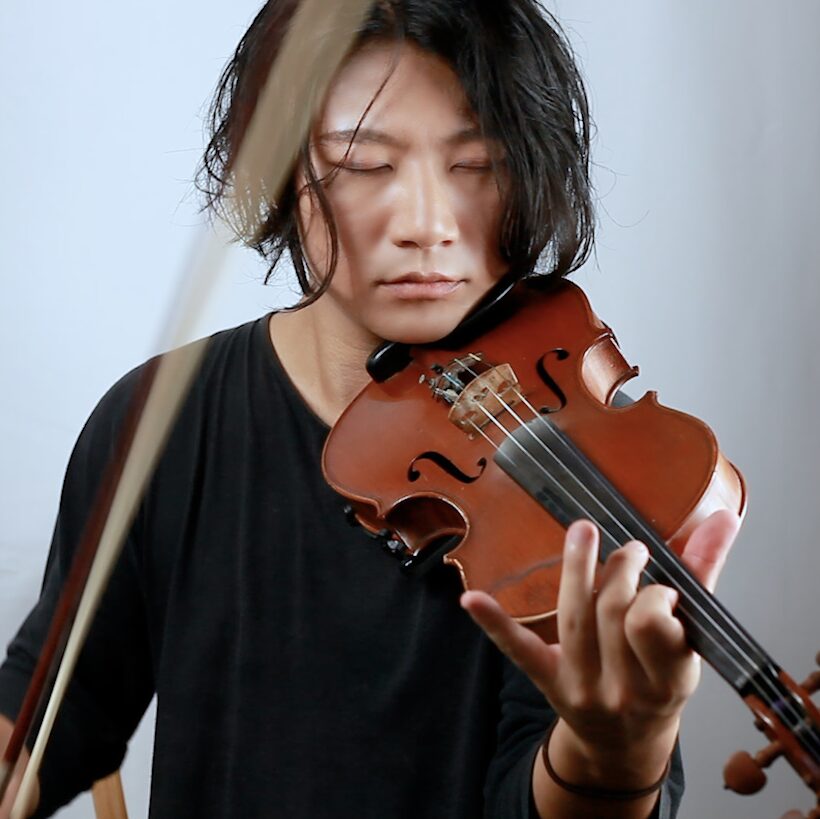
メールマーケティングに関するオススメ記事