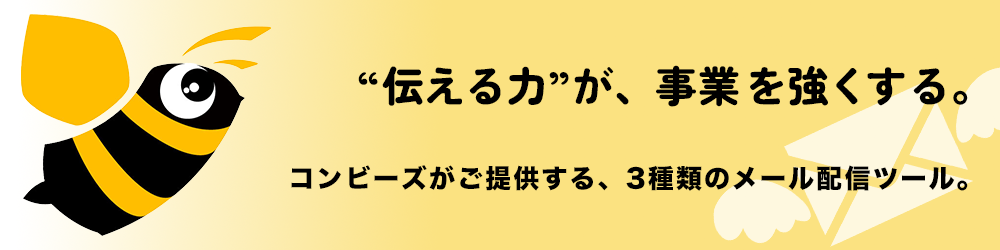新しい商品をつくる。
それは希望とリスクが複雑に絡み合う、未知への航海だ。
しかし、ひとつだけ例外に近い戦略がある。
「自分たちが本当に必要としたものをつくり、それを世界にも差し出すこと」
結論から言えば、この手法は驚くほど効率的で、そして美しい。
なぜならその出発点に、虚飾のない切実さがあるからだ。
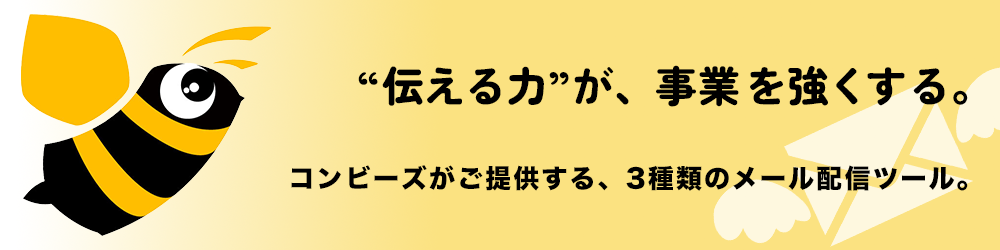
自社が必要なものは、社外でも必要かもしれない
商品企画はしばしば「市場の声」や「ユーザーインタビュー」から始まる。
だがもっとも深く、もっとも鋭い課題を知っているのは、
往々にして私たち自身なのだ。
自社が使うために開発する。そこにはふたつのメリットがある。
| ①自社が使うツールを自社で開発することは、長期的に見れば大きなコストダウンとなること。 ②自社における「生々しい必要性」を基点にしているため、同じ課題を抱える社外ユーザーが存在する可能性が高いこと。 |
だからこそ、内製したものを「ついでに」外販することは、理論上も実務上も非常に合理的だ。
海外ではこの考え方を「Scratch Your Own Itch(自分のかゆみをかく)」と呼び、
プロダクト開発の王道のひとつとして語り継がれている。
「必要」の外販で世界を変えたAmazon①
たとえば、Amazon。
インターネットバブルが弾けた2000年代初頭。
Amazon社もご多分にもれず、経営の危機を迎えていた。
コストダウンを検討していると、
そのほとんどを高額なサーバー代が占めていることがわかった。
しかし、自分たちの巨大ECサイトにおける
膨大な商品データや顧客情報を稼働させるためには…
当然、巨大なサーバーが必要だった。
「ならば自分たちで作ろう。」そして、Amazonは実行した。
インフラコストの80%ダウンに成功したとき。
CEOのジェフ・ベゾスは考えたのだった。
「Amazonのサーバーでは繁忙期以外の46週分、余剰が発生する。それを貸し出そう。」
この「必要」の外販こそが現在「AWS」と呼ばれ、
Amazon社全体の営業利益の6割以上を叩き出す怪物ビジネスに育った。
そしてAWSは世界の仕組みを変えた。
「クラウドサーバー」というサービス概念は、これまでになかったものだったのだ。
「必要」の外販で世界を変えたAmazon②
Amazonが世界を変えた事例は、もうひとつある。
世界一安く、をコンセプトとしていたAmazonは
倉庫管理や配送コストを下げるために自社で物流の仕組みを作った。
それをEC出品者へ向けて商品管理から配送、顧客対応まで
ワンストップにしたサービスとして提供した結果、
AmazonはECにおける配送の常識そのものを変えてしまった。
類似のワンストップサービスが世界中で横行し、
もはや送料無料が「当たり前」になったのである。
それがECに携わる者であれば知らない人はいない、
FBA(フルフィルメント・バイ・アマゾン)だった。
本気で自分たちが必要とした仕組みは、やはり
外の世界の「誰か」にとっても喉から手が出るほど必要だった。
「自社のため」を製品化して、改善する
Basecamp(旧37signals)はプロジェクト管理・チームコミュニケーション用の
クラウドサービスを提供している。
彼らが作ったプロジェクト管理ツールも、
最初は自社の案件管理をラクにしたいという願いから始まった。
そして結果として世界中のビジネスを支えるSaaSへと成長した。
また国産アウトドア用品メーカーであるモントベルは
創業者自身が登山家だった。
「自分が山で本当に欲しかったもの」を形にすることで
ヒット作を次々と生んだ。
また自社が「必要」とするツールを開発することは
ブラッシュアップの確実性にも繋がるといえる。
例えばMicrosoftではWindowsもOfficeも、まずは社内で
徹底的に使い倒す「dogfooding」を通じて改善され続けている。
自社で使うからこそ、欠点は誤魔化せない。磨く理由も尽きない。
結果として、ブラッシュアップされた上質な製品が誕生する。
プロダクトとは結局、作り手の痛みと体験量に比例するのだ。
落とし穴と、その対策方法
もちろん、このアプローチがノーリスクなわけではない。
外販する以上、市場不確実性・競合・価格設定・サポート負荷など、
対外ビジネス特有のリスクは必ずある。
そして何より危険なのは、
「自社がいま必要としているから」という理由で市場検証を怠ることだ。
自分たちの課題は深いが、狭すぎる可能性もある。
熱狂は盲目にもなる。
成功確率を上げたいなら、以下のプロセスが欠かせない。
| ①自分たちの本当に痛い課題にフォーカスして内製する 「便利なもの」ではなく、「なければ困るもの」をつくる。 ②社内で使い倒し、徹底的にブラッシュアップする 使い倒す。このサイクルがプロダクトの背骨を太くする。 ③同じ課題を持つ社外ユーザーを特定し、テストマーケティングする 共鳴する声があれば、そこから本格的な外販へ進めばいい。 |
この三段階を踏めば、
自分たちの世界から外の世界へ、プロダクトは静かに、確実に広がっていく。
メディア運営にも同じことがいえる
この間違え方は、なにも商品開発に限った話ではない。
たとえばメディアの展開においても、同様である。
自分やその周りが「欲しい」と思ったものを作る。
もし自分が食べることが好きならば、
グルメ情報メディア(例:美味散歩)を作れば
ユーザーの気持ちに立って運営をすることができるだろう。
また自分が家族と出かけることが好きなのであれば
子連れお出かけ専門メディア(例:ひなどりとラパン)を作るのもいいだろう。
とにかく大切なことは、自分がひとりのヘビーユーザーであることだ。
| ・「欲しい」情報を正確に選んで伝える ・確実にブラッシュアップできる |
これが出来なければメディア運営はいずれ行き詰まる。
最後に
商品戦略とは、遠い未来を読み解く占いではない。
もっと近く、もっと深く、もっとリアルな場所にヒントがある。
会社に置かれた自分の机。
プロジェクト内容がメモされたホワイトボード。
チームの誰かがこっそり抱えている、言語化されない痛み。
そこに、次のヒットが眠っているかもしれない。
私たちコンビーズも、自分たちで販促やコミュニティづくりのための
メルマガを発信して研究している。
そしてそこで生まれた「もっとこうしたい!」を製品に日々、取り入れている。
「自分たちが本当に必要としたものを開発する」
このシンプルで力強い原則こそ、もっとも美しい商品戦略だと考える。
参考資料
この記事を書いた人